MESSAGE
理事長メッセージスローガン、理事長所信

一般社団法人高槻青年会議所
第58代 理事長
竹中 健
Takenaka Ken
2024年度スローガン
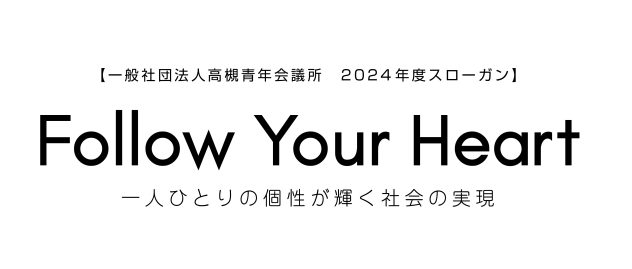
理事長所信
はじめに
青年会議所は、本当に「社会により良い変化」をもたらすことができているのでしょうか。
JC 運動とは「地域社会を持続的に発展させていく仕組みを創ること」を指します。それ であれば、一度きりの講演会やイベントで終わらせることなく、本気で地域社会の持続的な 発展を目指し、希望をもたらす変革の起点を創ることができれば、JC 運動の先に「社会の より良い変化」を生み出すことができるはずです。
しかし、その青年会議所の無限の可能性に、実は私たち自身が気付くことができていない のかもしれません。
それはなぜなのか。会員それぞれに入会動機があり、地域のこと、日本のことをいきなり 真剣に考えろと言われても難しく考えてしまい、きっと「自分事」だと捉えられていないか らなのではないでしょうか。
自分、家族、地域、大阪、関西、日本、そして世界。
自分事だと思える範囲が広がっていけば、視点が変わり、意識が変わり、行動が変わって いくはずです。
つまり、地域を変えることも、日本を変えることも、どこまでいっても「自分」を変える ことの延長線にしかないと私は考えています。
地域や日本を変えようと考えるのではなく、まずは自らの心に問い、自らを律し、自らの 意志で、自らの人生を切り拓いていく。
私たち会員一人ひとりが徹底的にセルフプロデュースを行い、より大きな希望を持ち 日々輝いていれば、高槻青年会議所は社会をより良くするための本気の運動を創る団体に なることができると確信しています。
Follow Your Heart
社会により良い変化をもたらすための答えは、きっとあなたの心の中にあるはずです。 自らを変え、地域を変え、日本を変える本気の挑戦を一緒に始めましょう。
成長を実感できる組織運営
青年会議所のミッションは「青年が社会により良い変化をもたらすためにリーダーシッ プの開発と成長の機会を提供する」ことです。我々はその使命を忘れることなく、会員が成 長を実感できる組織運営をしていかなければなりません。
青年会議所の会員は、各々家族を持ち仕事をして日々暮らしている中で、自ら年会費を払 い明るい豊かな社会の実現のためにボランティアで活動しています。だからこそ、他人に与 えられた目的のためではなく、自ら目的を定め、その目的達成のために全力で努力をし、結 果をつかみ取りに行く気概が必要です。その経験の先にある「まだ出会ったことのない自 分」に出会える感動と成長を感じられる組織運営を目指してまいります。
さらに、成長を実感できる組織になることができれば、会員一人ひとりがおのずと胸を張 って高槻青年会議所を周りの友人・知人に紹介できるようになるはずです。青年会議所の魅 力を頭で語るのではなく、心で語る。そうすれば必然と我々の仲間は増えていくはずです。 加えて、属人的な動きではなく、組織全体で責任を持ち会員拡大に取り組んでまいります。 JC の理念に共感した仲間を増やし、地域により大きな貢献をすることで、これからも高槻 青年会議所はまちに必要とされる組織であり続けます。
多様な社会を生きる青少年育成
急速なグローバル化や情報化の進展により、これまで正しいとされていたことや1 つの 価値基準で人生を描くことが困難な時代になっており、閉ざされた日本社会の中だけでは 生きることは難しく、世界の潮流の中で強く生きていくための青少年育成が求められてい ます。そのような多様な社会をこれから生き抜いていく子供たちには、人種・国籍・性別な どの表層的ダイバーシティに加え、価値観やパーソナリティなど認識しづらい深層的ダイ バーシティに対する理解を養う必要があります。あわせて、他者を尊重し協力・協働してい くためには、自らの中にある答えを自ら見つけ出し、自分を大切に思える力として自己肯定 感を育む必要もあります。世界で活躍する人材を育成するために、自分を大切にし、他者を 尊重できる力を養い、語学力向上だけに留まらない国際感覚が豊かなグローバル人材の育 成に取り組んでまいります。
また、他者に感謝し思いやりを持った青少年の育成のためにはスポーツを通した学びも 適切だと考えます。日本の伝統的スポーツである相撲を通じて、勝負の勝ち負けではなく 「挑戦することの意義」を感じてもらうことで、新たな挑戦を目指す子供たちの健全育成に 努め、子供たちの強くしなやかな心を育んでまいります。
地域を牽引するリーダー育成
日本は人口減少・少子高齢化により今後より一層の国内市場の縮小が進む中で、これまで 以上にイノベーションが生まれづらい環境に置かれており、さらなる経済成長の停滞が危 惧されています。また、AI やIoT などの急速なデジタル化が進む時代において、人々の働 き方は大きく変革を求められています。地域リーダーの育成というミッションを持つ青年 経済人の団体である高槻青年会議所には、ともに地域経済を牽引するリーダーの発掘・育成 支援に取り組む責任があります。デジタル技術を駆使しながらイノベーションを生み出し やすい地域づくりを行い、地域の次世代のリーダー育成に取り組むことで、地域経済の発展 に邁進してまいります。
また、答えがなく将来予測が困難な時代において、地域を牽引するリーダーには課題を自 ら設定し、多様な社会の中で様々な手法を用い解決する能力が求められています。社会の閉 塞感を打破し、希望が溢れる社会を創っていくために、これまでの常識や当たり前だと考え られていることに対しても疑問を持ち、自ら積極的に課題を設定し、解決に取り組む課題創 造型人材の育成に取り組んでまいります。
強靭で持続可能なまちづくり
近年、温室効果ガスによる温暖化に伴う豪雨災害や猛暑などの異常気象、化学物質が排出 されることによる人や動植物への悪影響等の「環境リスク」が大きな問題として叫ばれてい ます。SDGs でも目標として掲げられているように、持続可能な社会の実現のためには、私 たちが住み暮らすこの地球の環境を守るための具体的な行動が求められています。国内外 の環境問題を啓発する機会を創出することで一人ひとりの環境問題に対する意識醸成を図 ることや、ごみの発生抑制や再利用に対する市民の意識を高め、5R の取り組みを推進する ことで、環境リスクに対応したまちづくりに取り組んでまいります。
また、地震や台風、水害・土砂災害などの「災害リスク」も対策が必要な問題です。我々 が住む高槻市・島本町においても、2018 年の台風21 号による豪雨災害や大阪北部地震な ど、近年相次いで発生した自然災害により大きな被害を受けました。さらに、今後40 年以 内に90%程度の確率で発生すると言われている南海トラフ地震のリスクも抱えており、災 害リスクに対応したまちづくりが求められています。自助・共助・公助の強化のために行政 機関や関係団体との連携を行い、災害に強いレジリエントな地域社会の創出を進めてまい ります。
誰一人取り残さないまちづくり
インクルーシブの概念が語られるようになり久しいですが、教育分野や福祉分野だけで なく、各企業においても提供する製品やサービスに対して、インクルーシブ社会の実現に向 けた取り組みを始めています。行政機関や企業の商品・設計・サービスなどにおいて、イン クルーシブな「もの」や「こと」が増えていくことで、多彩な個性を持つすべての人々が、 より大きな希望を持ち、機会に満ちている社会に変えていけるはずです。だからこそ、年 齢・性別・国籍・障がいの有無・価値観等に関わらず、すべての人々がそれぞれの個性を発 揮して社会に参画し、お互いに多様性を認め合いながら共生し、住み慣れた地域で幸福を追 求できる「インクルーシブ社会」の概念の普及に努め、誰もが自分らしさを実現できるまち づくりに取り組んでまいります。
また、2025 年に開催を予定している大阪・関西万博も誰一人取り残さないまちづくりの 1つの大きな契機になると考えます。大阪・関西万博のテーマである「いのち輝く未来社会 のデザイン」は、「誰一人取り残さない」を理念に掲げているSDGs と合致するものです。 中長期ビジョンでもSDGs の推進を掲げており、大阪・関西万博の開催地である大阪府内 で活動する高槻青年会議所としては、この絶好の機会を活用しない手はありません。大阪・ 関西万博にかかる運動を通じて、SDGs のさらなる普及に努めるとともに、地域の企業・団 体の発掘と成長を目指してまいります。
組織内外に向けたブランディング構築
地域の人々や会員から高槻青年会議所の運動への共感を得るためには、組織内外への発 信方法や頻度はもとより、その運動の「目的」や「理念」を丁寧に伝えていくことが必要で す。
まずは、地域の人々に対するアウターブランディングを推進してまいります。我々がどの ような想いや理念を持って活動に取り組んでいるのかについて、SNS やWEB サイトを活 用し、何をするかだけでなく、その運動に取り組む背景や目的を重視した情報発信に取り組 みます。アウターブランディングの実施の先に、高槻青年会議所のファンを獲得すること で、地域で長く愛され続ける団体を目指します。
また、共に活動する会員に対するインナーブランディングにも取り組みます。青年会議所 で活動する私たち自身が、青年会議所運動の価値を正しく理解し共感していなければ、JC の理念を地域に伝播させることは難しいものになるでしょう。だからこそ、団体としての方 向性や目標を明確にし、組織内の共通認識を広めることで、会員一人ひとりの青年会議所運 動に対する姿勢の変化を生み出し、その先にある団体価値の向上や地域発展につなげてま いります。
時代に即した弛まぬ組織改革
価値観の多様化が進む現代において、これまで正しいと信じられてきたやり方や考え方 が通用しなくなってきています。地域社会をリードする団体だからこそ、そのような時代に おいて護るべき価値と革めるべき価値を見極め、新しいことにも果敢に挑戦し、時として現 在の常識とされていることを疑い、壊すことも躊躇わない姿勢が求められると考えます。
これまでの取り組みを否定することなくその意義を見つめ直すことで、発展的改革に着 手し、多彩な価値観を持つ会員が前向きに青年会議所で活動することができる環境整備に 取り組みます。また、それは一過性のものではなく、常に問い続けることこそに意味がある ため、採用しているルールや組織体制の目的や価値を明文化し、今後も時代に即した弛まぬ 組織改革をし続けられる素地を次代に受け継いでまいります。
おわりに
かの高名な芸術家であるパブロ・ピカソが残した言葉に「できると思えばできる。できな いと思えばできない。これはゆるぎない絶対的な法則である」というものがあります。
電気を生活の中で利用できるようになったこと。
飛行機で空を飛べるようになったこと。
どこでもインターネットにつながるようになったこと。
例をあげると枚挙にいとまがありませんが、その技術が確立し普及するまでは、きっと世 間の人々にはこう言われていたはずです。
そんなことは絶対にできない、と。
しかし、先人の誰かが諦めず「できる」と信じて行動し続けたからこそ、いまでは当たり 前のものとして世間で受け入れられ、社会の維持と発展に寄与しています。これはテクノロ ジーの話だけに限らず、政治体制や経済システムなど、人類は幾多の挑戦と失敗を繰り返 し、少しずつ社会をより良いものに変化させてきました。
それはJC 運動においても同様です。
「自分たちにはできない」と思ってしまうようなことも、無限の想像力と弛まぬ努力の積 み重ねによって、それを実現させる確率を引き上げることは決して不可能なことではあり ません。さらに、たとえその挑戦が失敗に終わったとしても、次世代の仲間たちがその失敗 を糧にいつか成功につなげてくれるはずです。
だからこそ、自らの可能性を信じ、JC の可能性を信じ、恐れず挑戦し続けましょう。
その一歩が、あなたを変え、地域を変え、日本を変えることにつながるのですから。
あなたの心に宿ったドキドキを信じ、ワクワクする1年をともに描いてまいりましょう。
